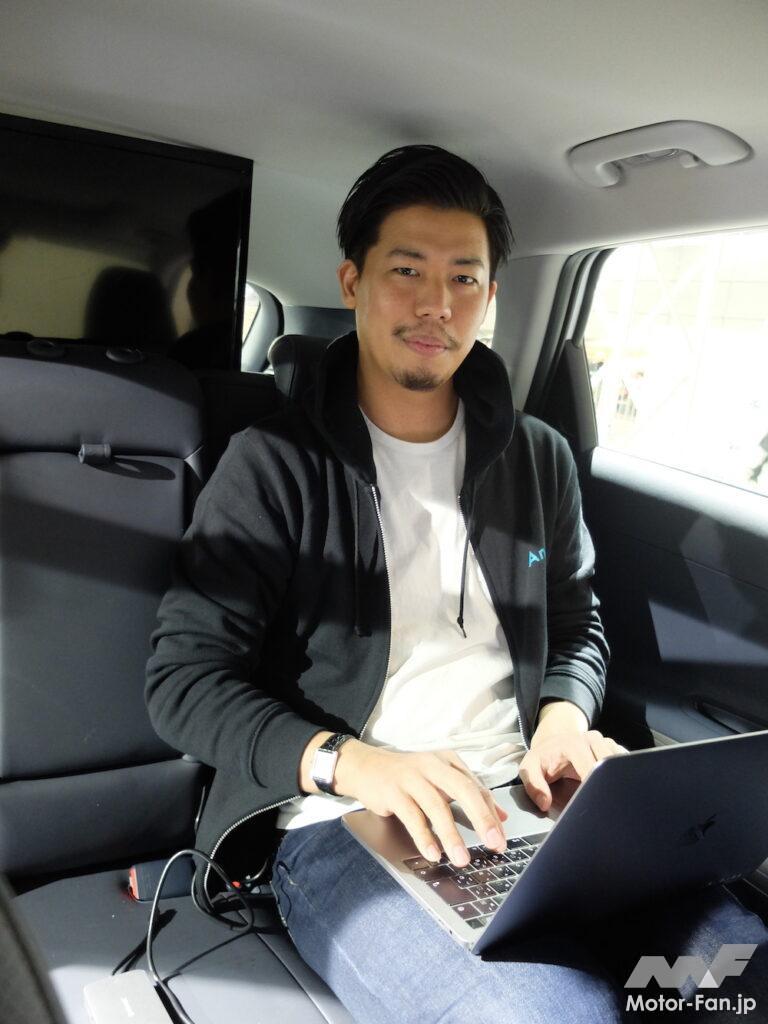自分のクルマをシェアする、あるいは個人所有のクルマのシェアリングを受ける。そのさきがけ的存在となったのがAnyca=エニカだ。これまでに例のない自動車をシェアリングするということなので、まだご存知のない方もいるかもしれない。
通常クルマを借りるのはレンタカーだが、個人のクルマをシェアリングするメリットとはどこにあるのだろうか。
馬場社長の説明によれば、一般のオーナーさんが日頃使っているクルマを利用できるということで、種類が多いということだ。現在、累積の登録は2万台に達し、車種数でいえばおよそ1000車種。
レンタカーではグレードが分かれており、それぞれが2−3車種といったところ。それも割とベーシックグレードである場合が少なくない。
対するエニカでは、1960年代あたりのクラシックカーから最新のモデルまで揃う。またオーナーがこだわって選んだ車種やグレードでもあり、カスタマイズされたものもラインアップされる。そのため、このクルマに乗りたいというモデルに出会えるのも大きな魅力だ。さらにはキャンピングカーや商用車など、用途に応じてベストな選択もできそうだ。
とりわけ最近増えているのが電気自動車のテスラ。モデルSやモデルX、そしてモデル3と現在100台弱ほどの登録がありさらに伸びているという。
今後ますます自動車のEV化は進むが、まだまだEVに乗り換えることに、色々な不安や疑問を持っている方も多いはず。そんな中で、試しにEV乗ってみるという利用の仕方もあるようだ。
また、クルマの受け渡しでオーナーと直接出会えることで、EVに対する考えや経験談を聞くこともできる。このあたりは、まずレンタカーではありえないコミュニケーションとも言えるだろう。
そして今回のインタビューの場となったのが、エニカのシェアリングするヒョンデ・ネッソの室内。オートサロン会場で展示し、インタビュールームとしても利用させてもらったが、ここに新しい展開がある。
ネッソは今後発売されるモデルだが、エニカではシェアリングのパターンとしてエニカ自身で所有したモデルをシェアリングするオフィシャル・シェアカーという形態も行ない始めている。非対面で舎衛リングできることも特徴で、そのモデルの1つがこの一般発売前のネッソだ。

このモデルは水素による燃料電池車で、水素を化学反応させることで生まれる電気を利用するEVで、排出するのは水だけの完全クリーン車。しかも水素フル充填の状態で820kmの基準走行可能距離を持つ。(社内測定値)
水素ステーションの拠点数はまだまだ少ないが、これだけの走行距離を持っていればかなり安心して使うことができる。ネッソは現在は東京都内に8台を配備しており、現在では未だ市販されていない最先端モデルだけに、どんなクルマかを探求できる楽しさもある。
加えて、ディーラーの試乗車などをシェアリングできるサービスも展開している。現在は、ほぼフルメーカーが登録されており、欲しいと思ったクルマにじっくりと試乗してみるという使われ方もしているという。
実際利用の仕方も簡単で、スマートフォンにアプリをダウンロードして免許などいくつかの登録をする。アプリでは、自分の位置の示された地図も表示されるので、近場にどんなクルマがあるかを確認しやすい。もちろん、場所を選んだり車種を選んだりすることもできるので、旅行先で使う、目的別で使う、こんなクルマに乗ってみたいなど、様々なニーズで利用することができる。
ところで累計登録台数2万台という数だが、業界トップのタイムズカーシェアリングが3万台。このタイムズは首都圏であればかなり多くの駐車場で見受けることができる。エニカはそれにはまだ及ばないものの、かなり近い形で登録されているようだ。タイムズは看板などで目につきやすいが、エニカは個人車の性格上、アプリで探すために目立たないだけで、実際にはかなり多くの登録数があるのだという。
単にシェアリングの時代というだけでなく、オーナーとしても自分のクルマを利用しないときに活用できるこのシステムは、これらのクルマ利用の流れとして便利で損のないサービスといえるだろう。
(公開インタビューの模様)
https://www.youtube.com/watch?v=6Hrv1eI0OTo