エントリー車唯一のスーパーカーは真紅のボディが美しいディーノ246GT
アルファロメオやランチア、フィアットなどの身近なエンスー車が多く集まる『さいたまイタフラミーティング』会場で、一際存在感を示していたのが、スーパーカーにカテゴライズされる真紅のディーノ246GTだった。
フェラーリ初のミッドシップレイアウトを採用したロードゴーイングカーであり、「フェラーリ・ディーノ」とも呼ばれるこのクルマだが、フロントエンドには跳ね馬のバッジはつかず、黄色字にDinoと書かれたエンブレムがあるだけだ。

フェラーリを名乗らなかった理由については諸説ある。その中でもまことしやかに囁かれているのが、このクルマに搭載される65度V型6気筒DOHCエンジンが、1956年に夭逝したエンツィオ最愛の息子・アルフレードのアイデアを元に開発をスタートしており、追悼の意味を込めて彼の愛称であるディーノと名付けたというものである。
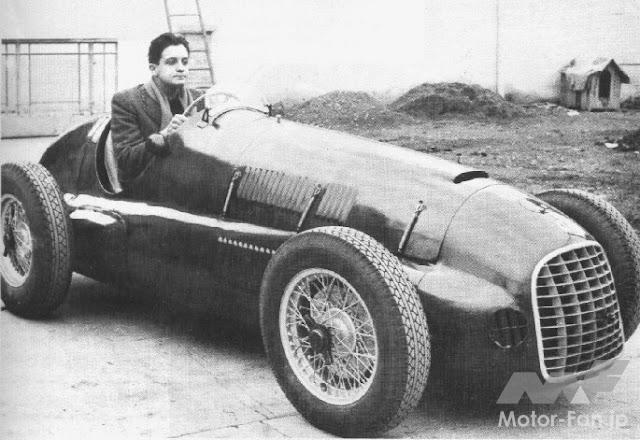
フェラーリ創業者のエンツィオと正妻ラウラの間に生まれた一人息子(現・フェラーリ副会長のピエロ・フェラーリは庶子で異母兄弟となる)。ボローニャ大学で自動車工学を学んだアルフレードは、V12エンジンを主力としていた当時のフェラーリ社も将来的には小型車を生産するべきとの考え方から、小型車向きのV6エンジンの開発に取り組んだと伝えられる。しかし、筋ジストロフィーにより24歳という若さで逝去。彼の死後、エンツォはディーノに搭載された65度V型6気筒DOHCエンジンはアルフレードの作品だと主張した。だが、実際のところ設計や開発の実務はヴィットリオ・ヤーノ技師によるもののようで、公道用の再設計はアウレリオ・ランパルディが担当しており、このエンジンの開発作業にアルフレードはほとんど関与していないようである。
しかし、実際のところは206/246GTの開発プロジェクトは、軽量レーシングミッドシップのディーノ206Sの公道バージョンとして仕立て直すところからスタートしており、ミッドシップ市販ロードカーの開発でライバルに遅れをとっていたフェラーリが、レースで活躍した206Sの輝かしいイメージを取り込みべく、ディーノのブランドを利用しようとしたというのが真相のようだ。

FIAのレギュレーション改定から始まる開発・生産計画
206/246GTに搭載される65度V型6気筒DOHCエンジンは、もともと2座レーシングカーとF2で使用される純レーシングユニットであった。しかし、FIAが1967年からのエンジンホモロゲーションを「年間500基以上の量産エンジン」と改定したことから急遽規定数を生産する必要に迫られた。

そこでフェラーリはこのエンジン生産数をクリアするために、フィアットの協力によって新型車を開発することにした。こうしてこのエンジンを搭載する3台の市販車が誕生する。
フィアットから発表されたのがディーノ・スパイダーとディーノ・クーペの2台であり、フェラーリが世に送り出したのが206GTであった。

フィアットが生産したスパイダーとクーペは初年度だけで2821台が生産されており、ホモロゲーション規定台数はこの2台だけで余裕でクリアしていた。フェラーリが206GTを開発したのはエンジンの規定数を生産するだけでなく、レースでの206Sの活躍のイメージを巧みに利用しつつ、V12モデルと比べて安価なロードカーを販売することが目的であったと考えられる。

前述の通り、フェラーリが206GTを開発するに当たって下敷きとしたのが206Sで、エンジンは基本設計を流用しつつ、細部を見直した上で使用しており、居住空間拡大のためエンジンは縦置きから横置きへと変更され、組み合わされるトランスミッションは2階建構造へと改められた。ボディはフェラーリ伝統の鋼管フレームにアルミ製のパネルが架装されている。
コスト低減とロードカーとしての扱いやすさを狙ってマイナーチェンジ
1968年、150台を生産したところでホモロゲーション規定台数を満たした206GTは、もはや2.0Lの排気量にこだわる必要がなくなり排気量を2.4Lへと拡大。それに合わせて車名も246GTへと変更された。
246GTは206GTの基本設計を踏襲しながらも、ロードゴーイングカーとしての扱いやすさと製造コストの低減を狙って随所に改良が施されている。だが、スタイリングに大きな変更はなく、操縦安定性向上のためホイールベースが60mm拡大されたのに伴って、全長とエンジンフードがわずかに長くなったことと、燃料キャップの位置が移動したくらいだ。

エンジンは排気量を拡大しただけでなく、軽合金を多用し、職人によるハンドメイドで製造されていた生産工程を見直し、生産コストに優れたアルミ製ヘッド+鋳鉄製ブロックエンジンへと変更を受けている。排気量の拡大によりトルクが厚くなったことに加え、前述のホイールベース延長や燃料タンクの拡大も相まって公道での扱いやすさは大きく向上している。
ボディパネルが製造コストの問題からスチール製に変更されたことから車重も重くはなっているが、排気量が2割アップしたことにより動力性能的には206GTとほぼ遜色がないものとなっている。

246GTは1969~1974年にかけて生産された。生産時期によりティーポL、ティーポM、ティーポEの3タイプが存在し、装備や細部の意匠がわずかに異なる。最終的に生産台数は3761台に達し、フェラーリとしては空前の成功を収めた。246GTのヒットにより、1973年には心臓部をV8とした後継の308GT4が登場し、以降308、328、4座のモンディアルとピッコロフェラーリの系譜が続くことになる。
創刊間もないTipo誌の連載マンガに登場した個体だった!?
今回の『さいたまイタフラミーティング』にエントリーしていた246GTは、31年前に刊行された『Tipo』(ネコ・パブリッシング刊)に登場した車両だ。と言っても、グラビアページで車両取材を受けたマシンというわけではない。連載マンガ『桜新町の懲りない面々』(作画:広井てつお、構成:中山蛙)のVol.7『跳ね駒に乗った花嫁』に登場した車両なのだ。

この作品は創刊間もない頃の同誌編集部員を中心とした登場人物がクルマにまつわる何気ない日常のエピソードを車両紹介とともに綴るというもので、246GTが登場するエピソードは、ガレージで愛車を弄る主人公のもとに、ディーノに惹かれた女子高生が通うようになり、クルマが縁を取り持ったことでふたりがゴールインするという内容であった。
当時、Tipoを毎号愛読していた筆者もこの漫画を読んでいた。だが、なれそめから若干の紆余曲折を経てハッピーエンドで終わる物語に「そんなうまい話が現実にあるもんか」とやっかみ半分の感想を抱いた記憶がある。だが、品の良い年配のオーナー夫婦から「このディーノと私たちがマンガのモデルなんですよ」と言われて面食らった。「あのエピソードは実話だったのか」と驚かされた。
オーナーはティーポ掲載時から今日までこのクルマをずっと愛好しており、奥様とは漫画で描かれた頃とそのままに相変わらずの仲睦まじい様子。オーナー曰く「『跳ね駒に乗った花嫁』は31年経って『跳ね駒に乗ったババア』になった」と言ってはいたが、こうして夫婦揃って一緒にミーティングに参加しているところを見ると、美しくピカピカに磨かれたディーノと同様にふたりの愛情も不朽のものなのだろう。





















