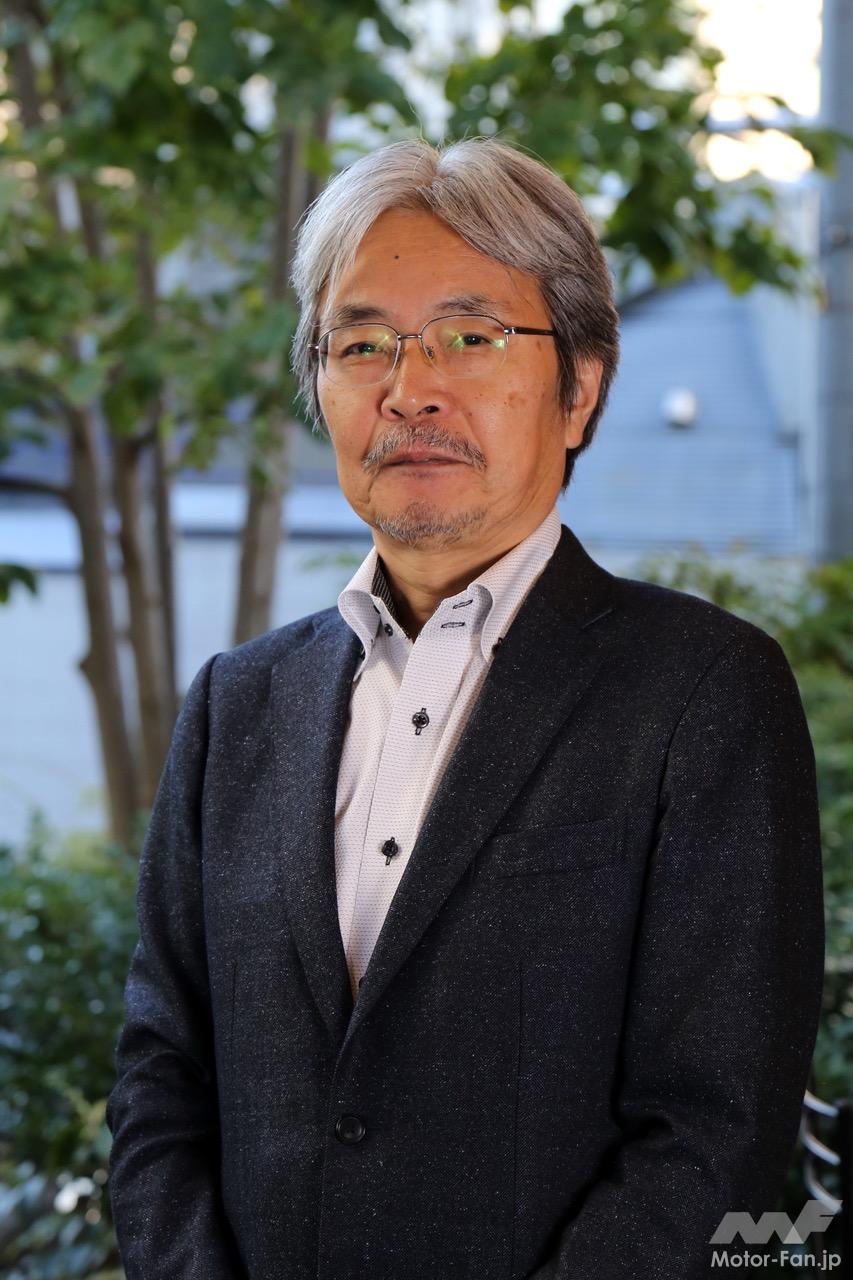目次
マツダ・マーケティング部門の決断で日本に帰還

「これを見られただけで、今日ここに来た甲斐がありました」とは、旧知の某編集者の弁。彼はMX-81がデビューした1981年の東京モーターショーを、リアルタイムで知る世代ではない。それでも42年も前のデザインが感動を誘ったのだ。
MX-81はイタリアのデザイン工房、ベルトーネがデザイン・製作したコンセプトカー。マツダ本社の試作倉庫に長らく眠っていたそれをイタリアに送ってレストアした経緯は、すでに3回にわたってMotor-Fan.jpでレポートした。その原稿を書いていた頃、MX-81はドイツのマツダ販売店のオーナーが運営する” Mazda Classic – Automobil Museum Frey”に貸し出されていたのだが・・。
続いて1985年のコンセプトカー、MX-03を取材するため昨年末にマツダ本社を訪ねたときも、ブランドアンバサダーの山本修弘(NDロードスターの開発主査)から「ドイツに貸し出す契約を1年延長した」と聞かされた。それが急転直下、”オートモビルカウンシル”に出品されたのはマーケティング部門の決断だったという。
「今までは日本で使い道がないから、ドイツに貸し出していた」と山本。しかし今年になって”オートモビルカウンシル”への出展が決定。使い道ができたとなれば、もともとマツダ本社の所有物だからドイツ側も嫌とは言えない。マツダは急遽、貸し出し契約をキャンセルしてMX-81を日本に空輸した。

見たことがないものを見せたい
今回の”オートモビルカウンシル”でマツダは、MX-30のR-EV(欧州仕様)を日本初公開した。ロータリーエンジンで発電し、モーターで走るPHEVだ。それゆえ出展テーマを「ロータリーの可能性の追求と新しい価値への挑戦」とし、1970年代のコスモAP、RX-8の水素ロータリー搭載車も展示。14日にプレスコンファレンスが行われている間、直4ターボのMX-81はブースの外側の通路に置かれ、スピーチしたグローバルマーケティング担当の青山裕大取締役もMX-81に触れることはなかった。
プレスコンファレンスでは言わば”ままこ”扱いだったMX-81だが、MX-30につながる”MX”の名を初めて冠したのがこのコンセプトカー。MX-30 R-EVのルーツであることは間違いない。ロータリーの歴史を語るコスモAPやRX-8水素ロータリーに加えて、”MX”の原点のMX-81を展示したのは巧いバランスに思えるのだが、会場でマーケティング部門の担当者に直撃すると少し意外な答えが返ってきた。
「”MX”という名前のつながりもあるのですが、それより来場者に何か今まで見たことがないようなものを見せたかったということが大きい。”オートモビルカウンシル”に相応しいものとして、MX-81を展示することにした」
その想いは、少なくとも初日午前中のプレス取材時間帯を見る限り、功を奏したと感じる。冒頭に発言を紹介した知人だけでなく、多くのメディア関係者がMX-81に注目。すでに定年退職した身ながら説明役を買って出た山本修弘は、大忙しの様子だった。

広いグラスエリアが醸す爽快なイメージ
それにしても、42年前のデザインが今でも見る人の心に響くのはなぜだろう? ここからは、その謎解きを試みてみたい。

まず、サイズ感と佇まいだ。MX-81は2代目ファミリアのフロアを流用している。現代のマツダ3に比べたらかなりコンパクトだ。それでもしっかりとした存在感があるのは、ボディサイドを前から後ろまで滑らかな樽形カーブで作っているからだろう。シンプルだが張りのある樽形カーブでボディサイドをまとめることで、フォルムに強いカタマリ感を与えている。
次に、広大なグラスエリア。なにしろベルトラインが異常に低い。普通ならベルトラインがありそうな高さでサイドウインドウを折り曲げつつ、グラスエリアを広げた。

現代のクルマのベルトラインが高いのは、2000年代に歩行者保護要件が導入された結果だ。ボンネットが60mmほど高くなり、それにつれてベルトラインも上がった。
セダン/ハッチバックでは、前後ピラーの位置と傾斜を変えずにベルトラインを上げれば、室内空間を犠牲にせずにキャビンを小さく=スポーティに見せられるメリットがある。そこに、もともとベルトラインが高いSUVの人気拡大が加わって、ベルトラインがどんどん上がってきた。

そうしたトレンドが生まれる前のデザインが、いかに健康的だったか? グラスエリアを極限まで拡大したMX-81が、それを教えてくれる。インテリアが開放感溢れることは、座ってみなくても想像できるだろう。移りゆく車窓の眺めを室内に目一杯取り込んでドライブする爽快なイメージを、誰でもすぐに抱くことができる。それが今では望み得ないことだからこそ、MX-81の広大なグラスエリアが現代人の共感を誘ったのではないだろうか。
機能をデザインするということ
MX-81のステアリングは、CRTメーターを囲むキャタピラ状のピースで構成されている。当時すでにLEDや光電管によるデジタルメーターが量産化されていたが、ベルトーネは一歩先を行ってCRTを採用。その画面を遮らないように、「キャタピラ・ステアリング」を開発した。

今やデジタルメーターは当たり前だが、それがステアリングに隠れないようにする苦心は相変わらず続いている。ステアリングの内側からメーターを見るようにすれば、どうしてもメーター面の一部がステアリングに隠れる。ステアリングの上からメーターを見るレイアウトでは、ドラポジとの整合性が課題だ。そうした今日的な悩みを42年前にすでに解決していたのが、MX-81のキャタピラ状のステアリングというわけである。


フロントシートはレバーひとつで回転し、外側に向くことで乗り降りしやすくする。シート自体は形状と表皮材で腰回りのサポートを強調し、そこから上のバックレストは細身にして腕の動きを妨げない。「大事なのは腰ですよね」と語りかけてくるかのようなデザインだ。


インパネ助手席側は箱形の大きな収納だ。リッドを開ければ、そこにはバニティミラー。定位置は水平だが、側面のボタンを押して斜めに押し込めば、ゆったりと脚を組めるほどのレッグルームが生まれる。
それらを山本修弘と一緒に確認しながら、彼が語った「ベルトーネは機能をデザインしていたんですね」という言葉に、思わずハッとした。2000年代以降のカーデザインは、ブランド表現に重きを置くようになった。2010年にマツダが始めた「魂動」はその代表的な成功例だが、そうしたトレンドのなかで私たちは大事な何かを見失っていたのかもしれない。
近年は「ユーザー体験」がデザインの大きなテーマになってきている。どんな体験価値を提供できるかが、カーデザイナーたちの最大の関心事。その観点でMX-81を見ると、今のクルマが表現すべき体験価値とは何かが雄弁に示されている。42年前のデザインが実はきわめて今日的なのだ。