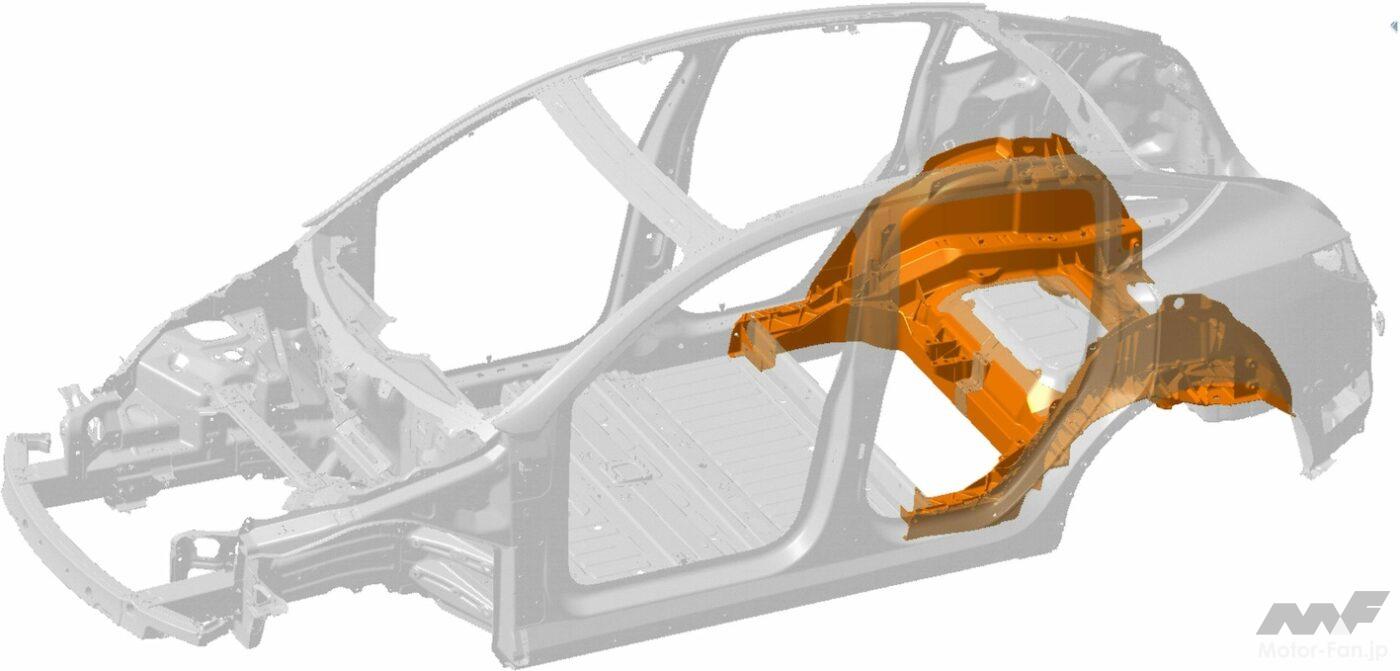連載
自動車業界鳥瞰図佐川急便とASFの小型BEVは型式認証をとれるか?
佐川急便とASFは2020年6月に「小型電気自動車の共同開発を開始する基本合意の締結」を発表した。その内容は「軽自動車規格のキャブバンを共同開発」「実証実験を行なう」というものだった。ASFはこのときに設立された「電気自動車の普及促進を図る」ことを事業目的としたファブレス(生産工場を持たない)企業であり、自動車の経験はゼロだ。そのため、車両開発の実務には日本のBEVベンチャーであるFOMMが協力することも明らかにされた。
そして昨年(2021年)4月、このプロジェクトは中国・広西汽車集団が量産を担当しASFが製品保証を担当するという内容に発展し、佐川急便は7200台を調達すると発表した。このときは具体的な車両諸元は明らかにされなかったが、現在AFSのホームページには全長3395mm×全幅1475mm×全高1950mm、最大積載量350kgと記載されている。日本の軽自動車規格の上限サイズであり、いま日本で販売されている軽キャブオーバーバンと同じである。

ステアリングホイールは左右90度ほどしか回らない。パドルスイッチをアクセルレバーとして使えるため、慣れれば足を使わないでも運転できる。センターインパネ上のD/N/Rスイッチで「前進/ニュートラル/後進」を切り替える。エアコン装備である点が生産国タイと設計国日本の気候を象徴している。
FOMMは日本企業であり、日本でBEVを設計しタイの工場で乗用車「FOMM ONE」を量産している。同車を設計したFOMMの鶴巻日出夫CEOはスズキ出身でありアラコ(トヨタ車体)では超小型モビリティ「COMS(コムス)」の設計に携わった。佐川急便向けの軽自動車規格バンBEVは当初、FOMMが設計し、「ONE」と同じインホイールモーター搭載の車両としてタイで量産するという青写真が描かれたが、そうするとコストが高くなる。そこで、FOMMではなく中国企業に量産を委託する方向に計画は変更された。
昨年4月時点でASFは、佐川急便への納車は2022年9月に始まり、「当面は並行輸入車として導入し、同時に日本の型式認証を受ける手続きも進める」と方針を語っていた。果たして国土交通省が型式認証を行なうかどうかは不明だが、FOMMがタイの工場から完成車輸入している「ONE」も並行輸入扱いであり、製造年月日証明など簡単な書類を提出すれば輸入できるという、2019年に改正された法令を利用している。
同じ仕様で継続生産される車両の場合、国交省は「年間200台程度までなら並行輸入として承認する」としている。並行輸入とは製造者(メーカー)との間に販売契約を結んでいない業者が輸入販売を行う方法であり、その歴史は長い。排出ガス検査で日本の規制を満たしていることが証明されれば販売できる。ICE(内燃エンジン)を持たないBEVは排ガス検査がないため並行輸入しやすい。
ただし、年間輸入台数が年間200台程度より増えると日本ではPHPの適用になる。PHPの認証を申請する場合は所定のデータを提出しなければならず、基本的には欧州基準であるECE、米国基準であるFMVSS、カナダ基準であるCMVSSのどれかに適合していなければならない。年間5000台までの輸入ならPHPが適用される。
佐川急便は7200台の導入計画であり、これを1年間で輸入するとなるとPHPの上限台数である5000台を超えるため、国交省の型式認証取得が必要になる。ここはさらにハードルが高く。複数台数の現車提出も必要になる。認証コストは5000万円以上になると言われる。もちろん、前述のECE、FMVSS、CMVSSのうちのどれかを取得していることが前提である。
前回お伝えしたように、中国基準であるGBを日本の国土交通省はまだ「相互認証」の対象として認めていない。「認める」とは、互いの基準の条文のひとつひとつについて「読み替え」を行なうことだ。中国基準に書いてあるこの記述はECEあるいはFMVSS、CMVSSの基準ではこの部分に相当し、内容は同一であることを日本と中国の基準担当者が相互に確認し合う作業である。
排ガスや衝突安全の基準を欧州から輸入した中国は、GBを「ほぼECE基準と同じ」に作った。「読み替え」さえ行なわれれば、日本が中国GBを「ECE基準と同等」と判断し、中国製BEVの輸入・販売には道が拓ける。そのためにはまず、日中双方の当局が話し合いをしなければならないが、現状では行なわれていない。並行輸入で年間200台程度を輸入することは可能だが、輸入台数が多くなればPHP対応が必須になり、その時点でGBは門前払いを食らう。
タイ製FOMM「ONE」を日本に完成車輸出する段階では、国交省との折衝が必要だった。FOMMはこのクルマを国際的な小型モビリティ規格であるL6/L7クラスではなく、純粋な乗用車としてのMクラスとしての承認を受けている。国際的には、日本の軽自動車は「L7」クラスと「M」クラスの中間であり、その点ではFOMMもL7認証を受けられる。しかし、日本はローカルカテゴリーである軽自動車の存在を脅かすL7は、なぜか過去に認証例がない。
ただし、Mクラスでの国内認証取得となると「普通の自動車」としての性能が求められる。海外から入ってくるクルマだけでなく、日本企業が軽自動車サイズのクルマを開発した場合、日本自動車工業会に加盟していない場合はほぼ認証取得は不可能だ。過去にそうした例がいくつかある。FOMM「ONE」がMクラスとしての国交省認証を取得したことは重要な前例である。今後、同様の寸法・重量のBEVが認証申請を行なった場合、国交省は「イヤ」とは言えない。
日本市場で中国車を「買える」か? 現状では難しい
欧州には運転免許の要らない「クルマ未満」の超小型車としてL6やL5というカテゴリーがあるほか、米国ではゴルフカートを一般公道で乗ることもできるが、日本にはそうした例外はない。道路運送車両法と道路運送車両の保安基準(これは法律ではなく国土交通省令であり、改定に国会の承認は不要)が適用されるためだ。その意味では、電動キックスケーターの公道走行が日本の一部で認められたのは、過去の例から言えば奇跡である。
日本に中国製BEVを輸入しようとしている人たちを取材すると、並行輸入としての申請受理、PHPの認証、型式指定というそれぞれの文言を混同している、あるいは全く理解していないケースが多いことに気付く。報道発表資料に「型式指定を取得」と書かれた例もあったが型式を取得すれば国交相が発表するほか官報にも記載される。ここを調べても、過去に中国車が型式取得した例はない。その理由は、前述のとおりの「読み替え」が行なわれていないことだ。
商用車の場合、PHPの申請も乗用車ほどは難しくない。比亜迪汽車(BYDオート)のBEVバスが輸入されたときも、商用車だからできたと言っていい。中国製乗用車では、第一汽車傘下の「紅旗(ホンチー)」とBYDのBEV「e6」の2台が日本で登録されたが、いずれも型式は「フメイ」という扱いである。FOMMによる「ONE」の並行輸入申請が受理されるまでには2年を要した。
日本市場で中国車を「買える」か……。
現時点での結論は「商用車なら可能性は高いが、乗用車は極めて難しい」である。世の中には誤解が出回っている。EU(欧州連合)でも、中国車はECE基準適合車としてではなくキットカー特例などで輸入されている。ECE基準取得の申請を中国の自動車メーカーは行なっていない。1車種あたりが少数でも、車種が多いためにEU向け出荷実績が1万台単位になっているだけだ。アメリカにはほとんど出荷実績がない。その理由は前回説明したとおり、事後認証制度の存在である。
自動車大国としての自覚と責任が、中国にはない
以下余談
筆者は新聞記者時代にUN-ECE(国連欧州経済委員会)のなかのWP29(ワーキングパーティ29=自動車基準認証分科会)と、日本の窓口機関であるJASIC(自動車基準認証国際化センター)をつねに取材対象にしていた。ジュネーヴまで出かけてWP29を取材した。日本のメディアおよびジャーナリストで筆者のような取材をしていた人には会ったことはない。自動車の基準認証というテーマを追い続けてきた自負が筆者にはある。
基準認証国際化は日本が世界をリードした。世界で基準が統一されれば、海外販売比率が高い日本の自動車産業にとっては利益になる。また、当時の運輸省、そのなかでこの分野を担当していた地域交通局陸上技術安全部自動車基準認証国際化対策室には理念があった。「その気になれば自由に世界を移動できる自動車に、基準認証という壁を作ってはならない」である。日本は基準認証国際化のホスト国になり、国際会議の場に各国を呼び、その必要性を訴え続けた。
その最大の成果は、排ガスと燃費の計測についての国際統一ルールであるWLTC/WLTPだ。中国とアメリカは採用していないが、それ以外の国と地域についてはWLTC/WLTPが多く採用され、ワールドスタンダードになりつつある。ただし、WLTC/WLTPの策定段階では、各国のデータを持ち寄り、詳細に検討する必要があった。自動車の基準認証を作る作業は面倒なものであり、時間もかかる。中国はそういう場に出てこない。WLTC/WLTPの議論にはオブザーバーとして参加したものの、基準採用は見送った。
たしかに中国は、いまや世界最大の自動車販売国である。しかし、国内に需要があるから無理して海外市場をめざす必要はない。中国政府は海外に国内データを出したくない。25年間中国取材を続けてきた筆者にとって、現在の中国には知的好奇心を掻き立ててくれる要素がない。過去にはアメリカが担い、日本がそれを引き継いだ自動車大国としての自覚と責任が、あの国にはない。











 中国製BEVの国際競争力 評価は過大か、それとも正当か「中国は欧米向け輸出に自信がない」
中国製BEVの国際競争力 評価は過大か、それとも正当か「中国は欧米向け輸出に自信がない」