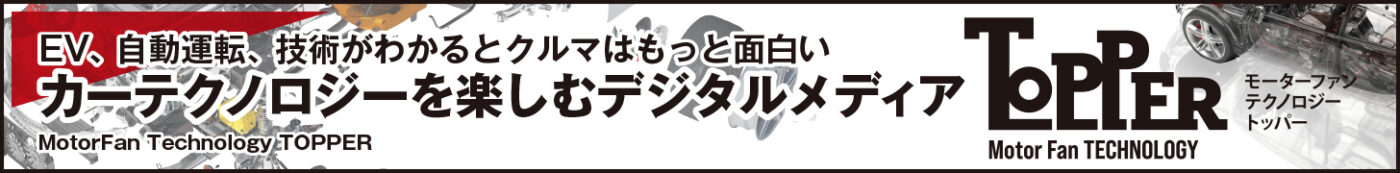日本の自動車業界がバッテリー電気自動車(BEV)の普及において遅れているとの指摘が多いが、その背後には複雑な電力供給の現実がある。日本の電力供給は火力発電が主体であり、再生可能エネルギー(再エネ)や原子力発電はそれほど大きな割合を占めていない。この状況は、BEVの普及がCO2排出削減にどれだけ寄与するのかという問題に影響を与える。
日本の場合、特に注目すべきは「マージナル電源」の概念である。これは「いま、そのBEVに充電している電力はどこから来たのか」を特定する手法であり、CO2排出削減の効果を正確に評価するために重要な指標となる。日本の経済産業省はこの考え方を基に、BEVと内燃機関車(ICE)のCO2排出量を比較している。
一方で、欧州連合(EU)はBEVを「CO2排出ゼロ」として推進しているが、その計算方法は「全電源平均CO2排出」という形であり、マージナル電源の考え方を採用していない。このような計算方法は、BEVの真の環境負荷を過小評価する可能性がある。
詳細はこちら→自動車の「現実」と「しがらみ」その1・電力の現実