東京モーターショーからジャパンモビリティショーへ進化した第一回のショーの第一回のトークセッションのテーマは「カーボンニュートラル×モビリティの未来」で、10月27日午後に開催された。ステージ上には、日本自動車工業会副会長を務めるスズキ代表取締役社長の鈴木俊宏氏とトヨタ自動車代表取締役社長の佐藤恒治氏らが登壇した。
トークセッションにはほかに、国土交通省 物流・自動車局次長の久保田秀暢氏、ExRoad 代表取締役COO/CMOの北原啓吾氏、Spiber 取締役兼代表執行役の関山和秀氏、BUSINESS INSIDER JAPAN 副編集長の三ツ村崇志氏が登壇した。モデレーターはモータージャーナリストの池田直渡氏。

日本はまったく遅れていない!
セッション冒頭で、池田氏が、日本はBEVで遅れているという論調があるが、CO₂削減という目的で見てもまったくそうではない、と切り出すと、スズキ社長の鈴木俊宏社長は
「うち(スズキ)は別に遅れていると思っていなくて、アメリカや中国、欧州を中心に走られているメーカーに言われているのかな。スズキはインドが大きな市場なので、やはり国や地域に適したカーボンニュートラルってなんなのかを考えていくのが一番必要だと思っています。EVに関して僕はトップランナーについていきますので。EVもちゃんとやります。だけど、インドだとメインじゃないのではないかなと思っています」と述べた。
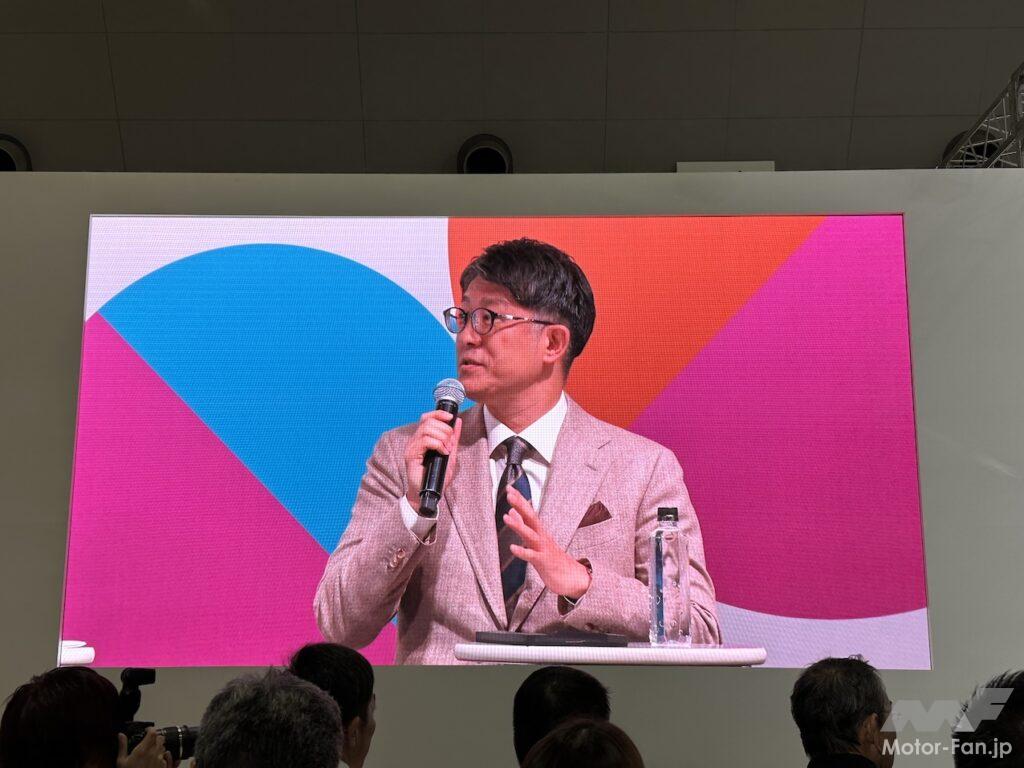
佐藤恒治社長は
「カーボンニュートラルという言葉が意味することをいま一度リマインドした方がいいんじゃないかなと思うんです。やはり敵は炭素で、徐々に減らしていって最後にニュートラルにするということだと思うんですよ。じつは日本は世界のなかでもっともカーボンリユースができている国なんです。ハイブリッド車の普及も早いしすでに2000年代から比べてら24%くらいCO₂を低減している、ある意味カーボンリユース先進国だと思います。その流れのなかで多様な選択肢を用意して、より早くカーボンニュートラルに向かっていくことが大事ですし、走行時のカーボンニュートラルだけじゃなくて、もっと広いカーボンニュートラルを理解することが必要だと思います」
ハードだけでなくソフトも重要
「カーボンニュートラル×モビリティの未来」のテーマに対して、使用時だけでなく、ものづくりを含めたモビリティライフサイクルの視点から脱炭素・地球環境を考えることの重要性や、国や地域によってカーボンニュートラル達成の方法は異なること、ハードだけではなく輸送効率といったソフトの問題、クルマを使う側・我々消費者側も一緒に協力しないと、カーボンニュートラルは達成はできないとの議論が展開された。
トラック業界のいわゆる2024年問題や高速道路における大型トラックの速度制限の見直しについても、国交省の久保田秀暢氏を交えて、白熱した議論が展開された。現在検討されている高速道路におけるトラックの最高速度制限の緩和については、果たして目論みとおりにCO₂を減らせるのか、逆に燃費効率の悪化に繋がるとの指摘もあった。
鈴木氏のインドでの取り組みが興味深かった。「牛のうんこの話」である。
「インドでは、牛のうんこを使ってバイオガスを作ろうとしています。インドにいつ牛の数ってご存知ですか? 3億頭いるんですよ。3億頭の牛糞をうまく使うと3000万台のクルマを動かすことができる。今インドの乗用車の保有台数が4000万台なので、75%のクルマを牛糞を使って動かすことができるということなんです。これがカーボンニュートラルになるのか。実は大気中のCO₂を草が光合成で取り込んで成長します。それを牛が食べてうんこを出します。で、メタンガスを出すことになるんですが、メタンガスの温室効果はCO₂の28倍です。もちろんクルマでバイオマスガスを使うとC0₂が出るのですが、トータルで考えると温室効果ガスの削減になっているということで、バイオガスを作ってクルマを動かそうとしてます」
トヨタの佐藤社長は、クルマ屋が造るEVについて、
「もっとシンプルで、どんなに時代が変わっても、クルマって楽しくワクワクするものでありたいなっていう思いだけなんですけど(笑)……というのと同時に、クルマの付加価値がどんどん高まっていって、社会システムに溶け込んでいくようなモビリティに変わっていく、そのきっかけがこのモビリティショーなんだと思うんです」と話した。ここで、開発中のAreneOSについても触れた。
「クルマの中のコンピュータというのは、機能ドメインごとにバラバラなシステムで動いています。本当に増築増築を繰り返してるので、先進安全はこのコンピュータがエンターテイメントはこっちでやってますみたいなことがあって、バラバラなものがひとつのクルマの中であたかも一体になって動いてるようになってるんです。それをガラガラポンして、OSを1個ちゃんと作ろうとしています。で、そのOSの上でいろんなものがプラグインできるようにクルマの価値を高めていけば、もっとモビリティとして価値が高まるんじゃないってことやってるんですね。そういう進化は、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)のようなものを生み出す原動力になっていって、自動車会社だけじゃなくて、多くの企業のスタートアップの方々も、つながり始める。例えば、AR的に街を走っていたら、その街の情報がクルマに自動的に取り込まれて、これはなんだろうって気になったらすぐわかるようなソフトウェアが差し込めたり、あるいは、自分のナビと連動して、自分が到着するころに、目的地の近くの駐車場をナビと連動して予約させてあげる。ま、いわゆるスマホってハードウェアは皆さん一緒でも、持っているアプリは全然違いますというようなことがこれからクルマに落ちてきて多様化が進んでいくと、もっともっとコミュニティの広がりってあるんじゃないかな」と語った。

第一回のは、500席以上ある会場が満席になるほどの盛況だった。異なる分野のトップランナーが集まって本音で会話することで生まれる「何か」があることを感じさせた。
「ジャパン フューチャー セッション」は、会期終了まで連日開催される。魅力的なプログラムが目白押しだ。ぜひ、聴きにいっていただきたい。
また、11月3日15時からは、日本カー・オブ・ザ・イヤーの「10ベストカー発表会」も開催される。こちらも、ぜひ多くの人に見ていただきたい。











