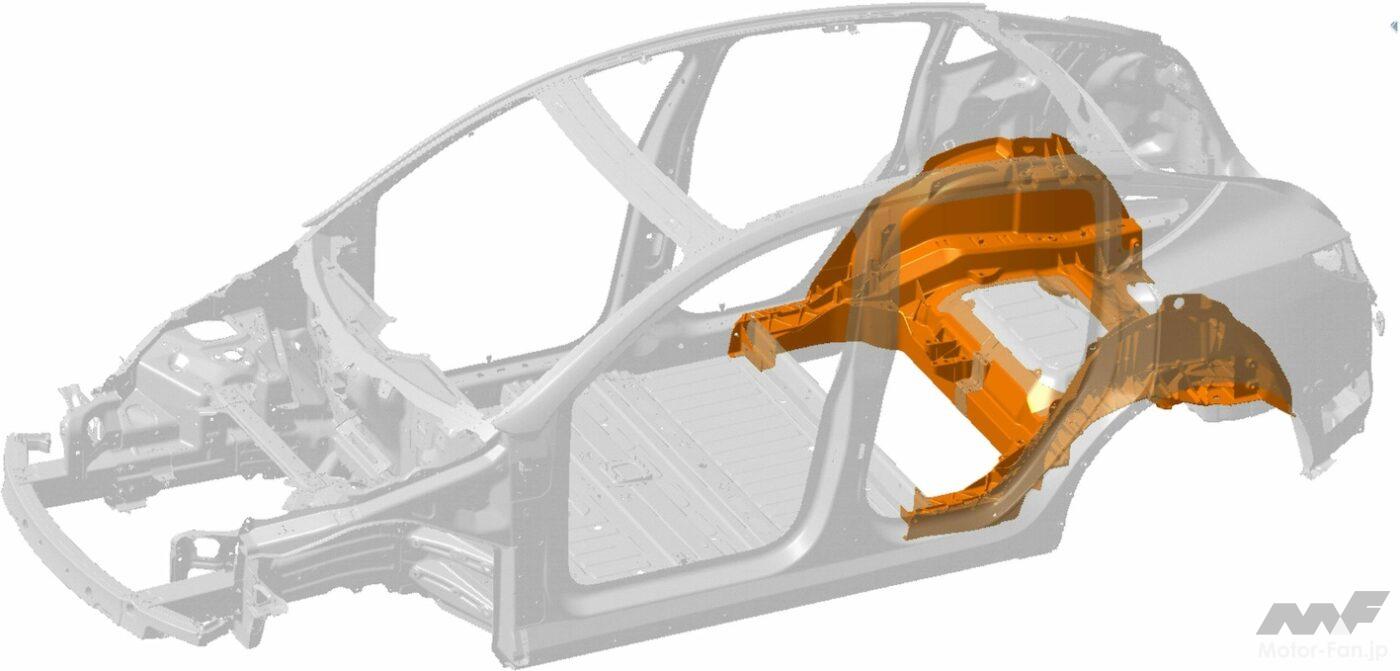連載
自動車業界鳥瞰図再エネ発電の「初期費用はかかるが、そのあとはどんどん安くなる」はウソ?
クルマを電気で走らせよう。そのほうが環境に優しい……世の中ではこう言われている。しかし、話はそこまで単純ではない。どうやって電気を得るのか。太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー(いわゆる再エネ)はたしかに有効な手段ではあるが、じつはこれらもそう簡単な話ではない。欧州では風力発電の「故障率」がすでに問題視されている。しかし、政策決定にはほとんど影響を及ぼしていない。

イギリスREFが発表した「風力発電の経済学、その現実と粉飾」と題した報告書には、欧州に設置されている洋上風力発電設備が、世の中に言われているほど「経済的ではない」との内容が書かれていた。このレポートを読むと、「再エネ発電はどんどんコストが下がる」という触れ込みはほとんど都市伝説レベルだと思えてくる。キヤノングローバル研究所の杉山大志氏がその和訳を国際環境経済研究所のHPで紹介しているので(ieei.or.jp/2020/11/sugiyama201124/)ご覧になってほしい。筆者は要点だけ説明する。


REFによると、英国の風力発電設備の平均運転費用は「使い続けているうちに増えている」という。グラフに時間経過と運転費用の関係を示した。2020年11月の報告なので、それ以降は「予測」だが、発電風車を所有・運営する350社以上の会計報告を元にしたデータなので信頼度は極めて高い。イギリスにも法律で定められた再エネ発電のFIT(固定価格買い取り制度)があるため事業者は発電量についてはウソをつけない。
興味深いのは、陸上風車でも洋上風車でも2008年までに設置された「比較的小出力のもの」、洋上については「水深10m以下の浅い海に設置されたもの」は1MW(メガワット)当たりの運転費用が安いことだ。しかし、2018年以降に設置された「より高出力なもの」、洋上については「水深30m以上の深い海に設置されたもの」は運転費用が高くなる。
そして、2008年設置の風車は発電費用がすでに運転開始時点の2倍に近い。2018年設置の風車は、まだ2年分のデータしかないが、その2年間だけで見ても発電費用が増えている。
あれ?再エネ発電は「設備を据え付ける初期費用はかかるが、そのあとはどんどん安くなる」のではなかったっけ?
発電出力の大きな風車は壊れやすい
デンマークのデータはもっと興味深い。陸上・洋上の風車約6,400基についての実際の「故障発生記録」がベースのデータであり、これも極めて信頼性が高い。「デンマークの発電風車の故障曲線」グラフを見ていただきたい。比較的小型低出力の陸上風車は、運転開始から年月を経るに連れて故障率がほぼ直線で高くなる。これはわかる。しかし、出力の大きい(つまりプロペラ直径が大きい)洋上風車は、運転開始からたった20ヵ月少々使っただけで全体の30%の設備に初期故障が発生している。

このグラフでの故障率1.00は「ぜんぶ壊れた」であり、0.80は「設備全体のうち累計80%が壊れた」である。運転開始から300ヵ月(25年)を経ても比較的小型の陸上風車は故障率70%。しかし、出力2MW以上の大型風車は運転開始から60ヵ月(5年)で全設備の約60%が壊れる。
また、運転開始から180ヵ月のやや手前で出力2MW以上の発電風車は故障率が横ばいになる。このグラフには200ヵ月付近までのデータしか示されていないが、その理由は2020年時点では運転開始からもっとも月日を経た設備でも200ヵ月と少々(16年と6ヵ月付近)がもっとも古いためだ。

運転開始から300ヵ月(25年)に近付いた陸上設置の1〜2MW出力の風車は、むしろ故障発生が落ち着きグラフのカーブが緩くなっている。この故障発生率は「熟成された技術」を使っている機械として「ごく普通」と言える。しかし、運転開始から20ヵ月も経たないうちに初期故障が発生し始めていたという現実は、日本の国産車に比べたら信頼性は低い。この程度の信頼性では、とても不特定多数の一般ユーザーには販売できない。
故障発生率のグラフからわかることは「発電出力の大きな風車は壊れやすい」ことだ。陸上設置でも洋上設置でもこの傾向は変わらない。発電出力はプロペラ直径にほぼ比例するから「大径プロペラを持つ発電風車ほど壊れやすい」と言い換えることができる。そして、陸上設置より洋上設置のほうが同じ風車の場合でも故障率は高くなる。
もちろん、故障しても修理はできるから、故障即廃棄ではない。とはいえ、修理にはお金がかかる。世の中で言われ続けてきた「再エネ発電のコストは、設備さえ導入すれば、燃料が要らないから発電コストはどんどん下がる」「発電量の大きい設備はなおさら発電コストの下げ幅が大きい」は、イギリスとデンマークのデータを見るかぎりはまったくのウソだ。
REFのレポートには「陸上設置の風車は年率約3%、洋上設置の風車では年率約4.5%で平均設備利用率が下がる」と記されている。平均設備利用率とは、365日24時間の中で「発電している時間」と同じ意味であり、すべての風車の平均値である。運転開始直後は設備利用率55%という優秀な風車もあるが、これは恵まれた気候条件がもたらした高稼働率である。
デンマークの首都コペンハーゲンとスウェーデンの都市マルメの間にあるエーレ海峡は、島を除くと幅13kmであり、高速道路と鉄道の橋がかかっている。そこから60km北にあるスウェーデンのヘルシンボリとデンマークのヘルシンオア間では幅4kmを切る。この一帯で筆者は風力発電設備の取材をしたことがあるが、しょっちゅう強い風が吹き、風力発電にはたいへん有利な場所だ。この付近に設置された洋上風車は設備利用率が55%程度になる。
ちなみに、日本の沿岸は平均すると設備利用率25%程度だろうと言われる。風力発電に有利な風が吹く地域では30〜35%との期待もあるが、現状では陸上風車の設備利用率は全国平均で約20%である。
REFのレポートによると、デンマークで平均設備利用率55%からスタートした洋上風車が、12年後には33%まで落ちる。また、洋上設置された2MW級の大型風車のケースを予測している。1MW当たりの発電コストは、運転開始初年度に24ポンドだった。過去5年間の平均レートは148円=1ポンドなので、このレートで計算すると約3,500円になる。
1MW(メガワット)は1,000kW(キロワット)、ただのワットに換算すると100万ワット。1メガワット=3,500円なら1キロワット=3.5円。これなら安い。しかし、12年後の予想発電コストは42ポンド。同じレートで計算して約6,200円。これは平均設備利用率からの計算であり、「故障のため発電していない風車」「修理のため運転を止めている風車」「部品の劣化によって発電効率が下がっている風車」の存在を合計したものだ。レポートを読むかぎり、累計の修理費用は加算されていない。
では、風力発電用の風車はどこ壊れるのか。次回はこのテーマを取り上げる。(後編に続く)








 最悪の故障で発電が2年も止まる。巨大風車は本当に「使える」のか?(後編)
最悪の故障で発電が2年も止まる。巨大風車は本当に「使える」のか?(後編)