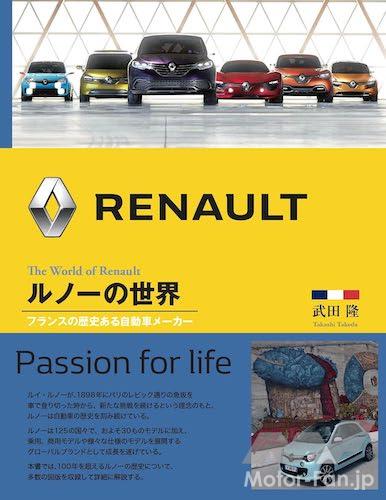日本人には理解し難く、もっとも遠い場所にあるクルマ……それがフランス車
みなさんは「仏国面」(ら・ふらっしぇる・さんと)という言葉をご存知だろうか? これは奇想天外なフランスのメカニズムの特徴を指したスラングである。曰く「ある問題を明らかに変態的な方法で解決しても“合理的”と判断すれば誰も止めようとしない」。「英国面」(ぶりてぃっしゅさいど)から派生した言葉であり、同様の言葉として「独国面」(どいっちぇらんとぜいて)、「米国面」(あめりかんさいど)、「日本面」(にほんめん)などがある(詳しくはインターネットで検索してみてほしい)。冗談めかしているが事の本質をついており、なかなか言い得て妙だ。

最近でこそグローバル化の波に晒されてだいぶ普遍性を持つようになったが、それでも門外漢からすれば理解するのが難しいのがフランス車だ。先日公開したシトロエン・エグザンティアに関するコメントには「全てがゴミ以外の何物でもない。仏製で人類に役立つ工業製品なんてない。ゴミを芸術と称する連中は別だが」(原文ママ)などと過激な言説を宣う御仁もいらっしゃった。
その気持ち、わからないでもない。日頃我々が慣れ親しんでいる日本車は、自動車黎明期はアメリカ車を、ある程度クルマ作りに習熟してからはドイツ車を手本に技術と商品力を磨いてきた。信頼性が高く、燃費が良く、実用性もあり、おまけにイージードライブで日本で使う限りはさしたる問題も生じない。そんな日本車に慣れたユーザーにとって、もっとも遠い場所にあるのがフランス車だからだ。
フランス車が一味違うのは開発したフランス人が見ている世界が我々と違うから
フランス車の中には常人の理解を超えたコンセプト、奇妙キテレツな設計、風変わりなスタイルのクルマも少なからず存在する。こうしたアクの強いクルマを目にして、ひょっとしたら「どうせワイン片手に酔っ払って設計したクルマなのだろう」と思う人もいるかもしれないが、それは大いなる誤解だ。
ジョン・レイノルズ著『シトロエン 革新への挑戦』(二元社CG BOOKS刊)や武田隆著『ルノーの世界ーフランスの歴史ある自動車メーカー』(三樹書房刊)あたりの本を1冊読めばわかることだが、彼らのクルマ作りは真面目も真面目、大真面目だ。
例えば、フランスを代表する大衆車のシトロエン2CVは「農村の人たちでも購入できる小型で安価な移動・運搬手段を作る」という社会正義と高邁な精神から生まれている。その結果生まれたのが「醜いアヒルの子」「ブリキの缶詰」「回る異状」と揶揄されたあのクルマなのだ。

おそらく、フランス人と日本人……いや、フランス以外の国の人と言っても良いのかもしれない……は、目に見える世界がまるで違うのだろう。論理思考回路が異なるとでも言うべきか? なんともなればフランス人は、世界で初めて革命で王を倒し、民主主義を実現した人たちでもある。その根底にあるのは徹底した合理主義と個人主義、他人や流行に流されない自我の強さだ。そんな彼らのモノ作りはひと味もふた味も違っていて当然だろう。それは1+1=2という小学生でもわかる答えを、わざわざ複雑な数式を使って導き出すようなもの。回答は正しい。ただし、数学者でもない限り、計算過程は盤根錯節なものに見えてしまうし、そのような計算式をなぜ用いたのかは、彼ら以外には理解しがたいことではあるが……。
ハマまる人はハマり、それ以外の人はそっぽを向く
しかしながら、フランス車の持つ世界観がある程度でも理解できるようになると、その開発理念と優れた合理性、時代を超越した先進的な設計による魅力に嵌まり込んでしまう。先ほども述べた通り、思考ロジックは異なるがクルマとしての有様はけっして間違っていないのだ。

それが証拠に初見では何ともとっつきにくい往年のシトロエンのようなクルマでも、3日も乗れば慣れ、1週間もすると設計や開発理念が理解できるようになり、1ヶ月が経つ頃には「もはやクルマはこれしか考えられない!」となってしまう。もちろん、そうした境地に至らず「こんなクルマ乗っていられるか!」とばかりに投げ出してしまう人もいるだろう。それはそれで構わないと思う。
信頼性よりも理想主義を優先するクルマづくり……そのワケは?
現在ではかなり改善し、かつてに比べればトラブルもだいぶ減ってはいるが、信頼性に関して言えばフランス車はお世辞にも褒められたものとは言えない。パーツの品質や工作精度は日本車とは比較するべくもなく、定期交換部品も多いし、ときには予期せぬトラブルに見舞われることもある。フランス車を過去6台乗り継いできた筆者もそれなりに苦労させられた。

だが、これはある程度は仕方がないことと割り切る必要がある。フランスに限った話ではないのだが、EUの前身となるEC(欧州共同体)の成立以前、欧州各国の自動車市場は極めて閉鎖的であった。高額な関税によって各国の自動車産業は手厚く保護されており、フランス人ならフランスのメーカー、イタリア人ならイタリアのメーカー、イギリス人ならイギリスのメーカーの中からクルマを選ぶのが一般的であった。

つまりこの頃の欧州は自動車メーカーの超売り手市場。自国市場を国内の数社で独占しているのを良いことに、各メーカーの技術者は自身の理想を具現化すべく、好き放題にクルマを開発できる環境にあったのだ。クルマづくりをする上で、商品性や信頼性、製造コストと理想主義を天秤にかけたとき、彼らは迷わず後者を選んだ。まさに究極のプロダクト・アウトの世界。自動車設計者とデザイナーのパラダイス。
愛車がトラブルを起こして割りを食うのは一般ユーザーであったが、彼らは自国製のクルマを買うしかなく、選択肢はおのずと限られているので、放っておいても高確率で自社製品をリピートしてくれる。そうした状況ならば手当てが後回しになるのは当然のことだろう。
強烈な個性が魅力を放つ斬新なクルマづくりこそがフランス車の持ち味
現在では欧州全体が巨大な単一市場になって自由競争が行われるようになり、欧州の自動車メーカーも世界規模のグローバル市場で成果を挙げなければ生き残りが難しい時代となった。とは言え、まだまだフランス車には古き良き時代の残滓が感じられる。メーカーごとの個性や独自性がだいぶ希薄化した現代でも、この国のクルマからは時折、全身個性の塊のようなクルマが登場することがある。大胆なコンセプトと設計者が理想とするカタチの具現化……日本のメーカーなら企画会議の段階で「顔を洗って出直してこい!」と一喝されて終わるであろうクルマが堂々と製品化されるのは、フランス車のフランス車たる所以である。

もちろん、こうしたクルマはアイデア勝負、斬新なコンセプト優先、スタイリング命なので、フツーのクルマなら重要視されるものが二の次、三の次とされることも珍しくはない。手段のためには目的を選ばないから屋上屋根を重ねるごとく怪怪奇奇なメカニズムだって許されてしまう。
機械は「同じ性能なら単純な設計のほうが高性能」とされるから、こうしたクルマは整備性が悪く、故障の発生率も高いだろう。でも、それで良いのだ。どうせフランス以外では数寄者しか買わないのだから。それが許されるのもこの国のクルマが持つ懐の深さなのだろう。
例えば『さいたまイタフラミーティング2023』で出会ったルノー・アヴァンタイムのように……。
クーペ×ミニバンのクロスオーバーコンセプト
「フランス車の個性が薄まった」と嘆く声がファンの間から聞こえ始めていた1999年。その年のジュネーブショーに1台のコンセプトカーが発表された。その名はルノー・アヴァンタイム。車名の由来はフランス語で「前衛」を意味するavant-garde(アヴァンギャルド)と英語で「時代」を意味するtimeを組み合わせた造語である。

ルノー製ミニバン・エスパスをベースにしたパーソナルクーペとして企画されたこのクルマは、全長4643mm×全幅1884mm×全高1600mm (生産型は全長4660mm×全幅1835mm×全高1630mm)と大柄なボディに3.0L V型6気筒DOHCエンジンを搭載。組み合わされるトランスミッションは6速MTがセレクトされていた。

クーペの魅力と言えば、何と言ってもスタイリッシュなエクステリアデザインと優れた走行性能にある。ところが、このコンセプトカーと来たら写真を見る限りスタイリングはお世辞にもカッコ良いとは言えなかった。いかにも鈍重そうなボディは6速MTを駆使したとしても、とてもスポーティな走りは期待できそうにもない。
上屋だけ見ればピラーレスハードトップの車体にストレートなボディラインの組み合わせは、たしかにスマートに映るのだが、ボディ下側半分はミニバンベースという出自からどうにもボテっとして重々しい印象を受けてしまう。
まさかの市販化!? ターゲットユーザーは?
1990年代中盤~後半にかけては新世紀を目前に控え、各国の自動車メーカーは従来のセダンやステーションワゴン、クーペ、SUV、ミニバンに代わる次世代の自動車像を模索していた。この頃ブームになったのが「クロスオーバー・コンセプト」だった。既存車種からの派生で作れるということで世界中の自動車メーカーが手を出し、その結果生まれたのが、コンパクトカーとミニバン、セダンとスポーツカー、ピックアップトラックとオープンカーなどの様々なクロスオーバーの一群であった。数多く生まれたクロスオーバーの中で残ったのが、現在世界的な流行になっているクロスオーバーSUVである。
次から次へと登場するこの手のクルマに少々食傷気味だった当時の筆者は、ジュネーブショーで発表された「ミニバン+クーペ」のアヴァンタイムを紹介する雑誌記事を見て「どうせ売るつもりはないのだろう」との感想しかなく、すぐに興味を失った。

ところが、である。それから2年後のパリサロンにブラッシュアップされたアヴァンタイムが再び出品されたのだ。聞けばこの斬新なコンセプトはそのままに市販化を予定していると言うではないか。まさに驚天動地。個性豊かなフランス車を見慣れたはずの筆者も、これには開いた口が塞がらなかった。「こんなヘンなクルマ、一体ルノーは誰に売る気なんだ……?」
アヴァンタイムの実車は想像よりもずっと美しかった
2002年、ルノーは満を持してアヴァンタイムを発売した。そして、本国デビューから間髪置かず日本市場でもデリバリーを開始したのである。カーイベントでこのクルマを目にしたファーストインプレッションは「写真で見るのとは違ってけっして醜いクルマではない」だった。

たしかに奇抜ではある。ベースがミニバンということもあり、大柄なボディにドアは巨大なものが2枚だけ。車体に比してどう考えてもドアの枚数が足りない。しかし、居住空間は広々としており、インテリアは大人4人が快適に過ごせるスペースが確保されている。車内の雰囲気は明るくクリーンで、まるでビジネスジェットのキャビンのようだ。シートベルトを内蔵したフロントシートはいかにも金が掛かってそうな作りをしている。どの座席もクッションは肉厚で、乗り心地も期待できそうだ。ピラーレスハードトップのボディは開放感に満ち満ちており、パノラミックルーフの前半分が開閉可能なので、サイドガラスを降ろし、ルーフを開ければドライバーとパッセンジャーはオープンカーのような爽快感を味わえるだろう。

ルノーはこのクルマにクーペを名乗らせていたが、既存のそれとは違ってスタイリングからは軽快感とかスポーティさは微塵も感じさせない。3.0L V6の心臓を備えていたとて、1.8tのボディを引っ張るには余裕があるとは言えず、とてもじゃないが熱い走りは期待はできそうにもない。
だが、考えてみればクーペ=スポーティカーである理由は必ずしもない。フランスは国土の2割程度しか山地のない平野の多い国だ。高速道路を淡々とスピードに乗って快適に走るハイウェイ・エクスプレスとしてなら性能は申し分ないとも言える。それにこの頃から街中で目立ち始めていた装飾過多で厳ついマスクの国産高級ミニバンと比べれば、周囲を威圧するような押し出し感はなく、それでいて高級車(新車価格525万円)らしい堂々とした風格を備えるところなどはむしろ好感が持てた。
非実用的なフランス製クーペは「陸を駆けるクルーザー」
実用面に目を移せば、二重ヒンジを使って狭い場所での乗降性に工夫されているドアだが、いかにも重そうで(実際に片側だけで53kgもある)、坂道にクルマを停めたときなどはドアの開閉に難渋するに違いない。また、大柄なボディにもかかわらずリアハッチの開口面積は期待するほど広くはなく、開口部下端が高いので荷物の積み下ろしもやりにくいだろう。パッケージングの優れたエスパスをベースにしたにも関わらず、設計には無駄が多くて、車格に応じたスペース効率を実現しているとは言えない。端的に言ってしまえば、実用車としてはなんとも使いにくそうなクルマではある。

だが、機能面から評価すれば赤点スレスレも良いところなのに、実車からは鈍重な感じをまるで受けず、不思議と人を惹きつける魅力があった。シンプルな面構成ながらサイドに流れるエッジの効いたキャラクターラインがシャープでクリーンな印象を与えるスタイリングとなっている。ディティールに至るまで神経が行き届いており、風変わりではあるが、不思議と機能美のようなものを感じてしまった。美の元となる機能がないにも関わらずに、だ。
この成り立ち、この雰囲気はまるで「洋上の別荘」と言われる高級クルーザーだ。すなわち、地を駆ける豪華なヨットである。実生活にはまるで役に立たず、存在自体ムダなものであるが、その優雅さ、贅沢な佇まいは多くの人が憧れ、クルーザーを所有できるようなゆとりのある生活は人々の心を惹きつけてやまない。そんなクルーザーにも通ずる無駄が、このクルマに余裕と贅沢さを与えている。手垢のついた表現で恐縮だが、これがフランス流のデカダンス、エスプリというヤツなのだろう。
総生産台数は2年で8557台……
商業的な失敗は高級パーソナルカーとしてのわかりにくさゆえか
ただし、アヴァンタイムの魅力や独自の価値観は本国フランスでも理解する人は少なかったようで、生産期間わずか2年、総生産8557台で製造は打ち切られている。
それはそうだろう。たしかにアヴァンタイムは他車にはない個性と魅力がある。けれども、だからと言って高級車としては極めてわかりにくい存在に、ポンと500万円もの大金を支払える人はそうはいない。高級車に乗る理由は人それぞれだろうが、購入動機に「人から成功者として見られたい」という見栄の要素、承認欲求の充足が含まれていることは否定できまい。

ところが、アヴァンタイムときたら実際にドライバーズシートに座れば悦楽の世界が広がっているにしても、側から見れば「ただのヘンなクルマ」にしか見えないのだ。フツーの人は同じカネを払うなら、メルセデス・ベンツやBMWを買う。こんなクルマを喜んで買うのはフランス車を愛好する数寄者だけだろう。
アヴァンタイムの失敗により製造元のマトラは自動車ビジネスから撤退
ルノーブランドで世に送り出されたアヴァンタイムだが、企画・開発・製造はルノーが手掛けたわけではなく、委託を受けたマトラ・オトモビルが担当している。
もともとマトラ(現在はMBDAに吸収合併されている)はミサイル製造から事業を拡大した工業コングロマリットで、その本業はあくまでも航空宇宙・防衛産業にあった。

1964年にミッドシップ・スポーツカーの始祖のひとつであったオトモビル・ルネ・ボネを傘下に加えたのをきっかけにマトラは自動車ビジネスに参入。自動車部門はマトラ・オトモビルを名乗った。
独立メーカー時代にはF1やル・マンなどのモータースポーツに集中し、市販車はスポーツカーしか手掛けないという放蕩ぶりであった。
結局、マトラ本体が自動車部門の嵩む赤字を看過できなくなり、1969年にクライスラー傘下のシムカと合併。シムカを含むクライスラー・フランスがPSAグループに売却されたあとは、ルノーと関係を結び、エスパスの開発・生産を委託されるようになった。だが、1990年代末に同車の生産がほかの工場に移されたことで、空いた生産設備の有効活用ということでアヴァンタイムの開発・生産を行うことにしたらしい。

当の本人たちは至って真面目だったのかもしれないが、外野から見ている限り、マトラ・オトモビルの自動車ビジネスは半ば道楽でやっているような印象だった。ルノーがプロジェクトを承認しているとはいえ、企画から設計・開発までを任されれば、本気で売れると思ってアヴァンタイムのようなクルマを作ってしまう。こんなクルマが成功すると思っていたのだから、このメーカーの商売感覚はやはりどこかおかしかった。
結果、同車が商業的に失敗したことにより、 本業にさして影響がないこともあってか、マトラ本体は自動車部門の閉鎖と撤退の判断をあっさりと下し、自動車部門をピニンファリーナに売却して幕引きを図った。つまり、アヴァンタイムはマトラ・オトモビルに引導を渡したモデルということになる。
退廃的な悦楽の世界に生きるアヴァンタイムは素晴らしい
そんなアヴァンタイムに『イタフラミーティング2023』の会場で久しぶりに出会うことができた。デビューから20年以上が経過した現在でも、パトリック・ルケマンが手がけたスタイリングは独創性と確信性に溢れる奇妙な美しさと妖しい魅力を放っており、古びた感じを受けることがまったくない。

当時、日本に正規輸入されたアヴァンタイムはわずかに206台。2.0L直列4気筒ターボを心臓に持つ左ハンドルモデルなどが、ごく少数が並行輸入されたようだが、いずれにしても極めて少ない数だ。モータージャーナリストの森口将之氏のような熱心なファンによって維持されている個体もあるのだろうが、現在の国内残存数は新車時よりも当然少ないだろう。

中古車情報サイトで確認したところ、2024年1月現在で販売されている中古車はわずかに4台だけ。希少車ということもあり、相場はあってないようなものだが、下限は支払い総額77.6万円で、上限は走行距離3.3万kmのローマイレージ車が243.8万円。昨今はヤングタイマー車の相場が上昇し、プレミアム価格で販売されることが珍しくなくなっているが、もともと不人気のアヴァンタイムの中古車相場はさほど影響を受けていない様子。
今後、アヴァンタイムが再評価される機会に恵まれるかはわからない。ひょっとしたら何かの弾みで相場が急上昇し、プレミアムカーの仲間入りをするかもしれないし、不人気車のまま商品として販売できるレベルの個体がなくなって、市場からひっそり姿を消すことになるのかもしれない。
しかし、世間での評価を別としてアヴァンタイムの独創性と存在感は今後も変わることはないだろう。さしものフランスでもこれほど大胆かつ個性の塊のようなクルマはもう二度と再びリリースされることはないのではないか?

アヴァンタイムにはフランス車としてのエッセンスがすべて詰まっている。それも戦前に失われたフランス製高級車のようなデカダンスの残滓を含めて、である。高級ソファのように分厚いシートに座れば身体を優しく包み込み、いざ走り出せば意外にもシャープなハンドリングを披露し、柔らかくも腰のあるサスペンションで道路の起伏を物ともせずハイウェイを矢のように疾走する。ここまではすべてのフランス車が持つ長所である。それはたとえ奇怪なコンセプト、奇妙キテレツな設計、風変わりなスタイルをしていてもフランス車の本分が実用車にあるからだ。
ところが、アヴァンタイムにはフランス車のもうひとつの長所であるハズの実用性やスペース効率を半ば無視して、ドライバーとナビシートのパッセンジャーに移動の悦楽を最大限与えることに重きを置いている。これは他のフランス車では考えられない、このクルマだけの特徴である。
そのことを知るのはアヴァンタイムのオーナーと熱烈なフランス車エンスージアストだけ。そんなこのクルマの魅力を知る人間にとって、世間の理解など取るに足らないこと。雨森芳洲風に言うのなら「大衆、いまだその楽しみを知らざるのみ」、尾崎紅葉風に言うのなら「おまえら、せいぜいつまらないクルマに乗って長生きしろ!」と言ったところか。たとえ常人には理解されずに「変なクルマ」扱いされたとしても、オーナーには今後もスノッブで極上なカーライフを楽しんでいただきたい。アヴァンタイムはまさしく上級者向け、自動車グルマンのためのクルマなのだから。
『さいたまイタフラミーティング2023』エントリー車レポート
イタリア車編はこちら!!
『さいたまイタフラミーティング2023』エントリー車レポート
フランス車編はこちら!!