トライシェビーの大成功によって
GMは大衆車の肥大化とデコレーション化を加速させる
トライシェビーのハイパワー&ゴージャス路線の成功に味をしめたGMは、消費者の購買意欲をくすぐるため、さらなる車体の大型化、エンジンの高出力化を図り、より速く、より快適に、より贅沢へと、製品を発展させるべく邁進して行く。

こうしてトライシェビーと入れ替わりに1957年秋に発表されたのが1958年型シボレーだった。このクルマのスタイリングはさらに派手なものとなり、装備を充実させ、ボディは大きく重く肥大化した。そして、巨大な車体を引っ張るのに265cu-inV8「ターボファイア」では荷が重いとばかりに、オプションとして新開発の348cu-in(5.7L)の排気量を持つビックブロックV8を用意している。


巨大化したシボレーはたしかに贅沢で快適、乗り心地はさらに良くなったが、反面トライシェビーが持っていたスポーティなキャラクターはだいぶ薄まった。しかし、未来への夢と科学技術と宣伝に溺れていた当時のアメリカの大衆は、このモデルチェンジを「アメリカの繁栄とテクノロジーによる勝利」として概ね好意的に受け止めた。そして、GMが先鞭をつけたこのデコレーション路線は、ライバル他社をも巻き込みなお一層加速して行くのである。

1960年代に入るとビッグスリーは拡大戦略によってラインナップを強化
アメリカのユーザーはメーカーの販売戦略に嵌って行く
もちろん、高出力のエンジンを積んだ大型車ともなれば相応に車両価格の上昇が避けられないが、ビッグスリーは消費者を取りこぼさないようにラインナップを強化して行くことで対応した。

1950年代まで各メーカーは富裕層向け・中流向け・大衆向けと販売チャンネルを3~5ブランドに分けた上で、それぞれのディビジョンは基幹となる単一車種をベースに、装備とトリムレベルに応じて差異を生み出すことで対処していた。しかし、1960年代に入る頃には、もはやそんな悠長な商売をやっているような状況ではなくなり、各ディビジョンはサイズと装備、価格によるヒエラルキーに支配された車格の異なる多種多様なモデルを次々に発売するようになった。

このように綿密なマーケティングによって自動車市場が首尾一貫して企業のコントロール下に置かれるようになると、ユーザーは好むと好まざるとに関わらず、どのブランドを選び、どんなクルマに乗るかよって、収入や社会的地位を周囲から推し図られるようになる。

すると、人々は「良いクルマか、悪いクルマか」「運転して楽しいか、楽しくないか」「自分の好みに合うか、合わないか」というオーナーと愛車とのプライベートな関係性だけでなく、愛車に乗る自分が周囲からどう見られ、どのように評価されるのかという社会性にも心を砕かなければならなくなった。これは常に他人の目を気にしながら「今の愛車は自分にふさわしいのか?」「もっと良いクルマに乗り換えるべきではないのか?」と、今の愛車に対して葛藤を抱き、神経をすり減らされながらステアリングを握ることを余儀なくされることでもある。

そして、そんな消費者心理を煽るように、ある日、自宅へ営業に訪れたセールスマンはユーザーの耳元でこう囁くのだ。「ご出世され、年収が上がったのですからいつまでもシボレーの大衆車に乗り続けていては世間体が悪いですよ。同じシボレーならもっと車格の上のモデルへ、それともいっそのことビュイックにでも乗り換えませんか?」と。

計画的陳腐化戦略のもとで目まぐるしく変わるスタイリング
その一方で社内で権力を持った財務部門が技術開発が抑制
しかも、この当時のアメリカ車は1年毎にマイナーチェンジが行われ、スタイリングは目まぐるしく変化した。そして、デビューから2~3年が経過する頃にはフルモデルチェンジされ、旧モデルとは似ても似つかないほど大きく姿を変えて行ったのである。機能的には何ひとつ不満なく、まだまだ使えるクルマがとたんに古臭く、乗り続けるのが惨めに思えるという仕組み……これを「計画的陳腐化」という。

これはGMの社長だったアルフレッド・スローンが1920年代に提唱した「スローン主義」によって提唱された販売戦略であり、アメリカが平和と繁栄を享受していた1950年代後半~70年代前半にもっとも激しく、かつ完成されたものになった。その結果、1970年代に入る頃にはビッグスリー各社のラインナップは大幅に拡充されてより複雑化した。
大衆ディビジョンであるはずのシボレーが、キャデラックとサイズもトリムレベルと装備もほとんど変わらない車種を売るようになり、各ディビジョンごとのキャラクターは曖昧模糊なものとなって、ほとんど選ぶところのない似たり寄ったりのクルマがショーウィンドウに並ぶようになった。
アルフレッド・P・スローンJr
(1875年5月23日生~1966年2月17日没)
コネチカット州ニューヘイブンで生まれたスローンは、ブルックリン工科大学で電気工学を学び、その後マサチューセッツ工科大学(MIT)に編入して1895年に卒業。1899年にベアリング製造会社のハイアット・ローラーベアリングの社長に就任。彼の手腕により会社は急成長し、1916年にこの会社は他社と合併してユナイテッド・モーターズ・カンパニー(現・ACデルコ)となるが、引き続き合併後も社長の座にとどまった。その後、この会社はウィリアム・C・デュラントが指揮した企業買収による拡大戦略によって同業他社とともにGMの一部になる。そこでスローンはアクセサリー担当副社長および執行委員会のメンバーに任命された。その後も彼はGM内で着々と出世を重ね、GM副社長を経て1923年にGM社長となった。社長時代のスローンは「スローン主義」と呼ばれる企業戦略を打ち出し、利益率を上げる会計手法の導入、消費者の購買意欲をくすぐるための毎年のスタイリング変更(=計画的陳腐化)、シボレー・ポンティアック・オールズモビル・ビュイック・キャデラックの各ディビジョンが互いに競合しない価格体系を確立し、GMの顧客は収入や年齢の増加とともに購買力や好みが変わってもサイズと装備、価格にヒエラルキーに支配されたGM車の中から愛車を選ぶように仕向けた。また、彼の功績は関連会社に金融部門を設立したことにもあった。それまで消費者がクルマを購入するには何年もかけて貯金する必要があったが、副社長時代の1919年に彼が主導してGMアクセプタンス・コーポレーションを設立し、自動車ローンを展開したのだ。これによりGMの顧客はライバル他社に先駆けてカーローンを利用が可能になった。これによりGMは好調な業績を上げたが、その一方でバッジエンジニアリングによる類似車種の乱立、陳腐化したコンポーネントの永年にわたる使い回しなどの弊害も産む結果になった。1937年、スローンは取締役会会長に就任するが1946年に辞任し、これを最後にビジネス界を引退(同時に終身名誉会長の肩書が与えられる)。以降は1966年に亡くなるまで自身が設立した「アルフレッド P. スローン財団」を通じて、慈善活動に時間とエネルギーの大半を捧げた。私生活では趣味らしい趣味を持たず、読書もほとんどしないスローンであったが、1963年に『GMとともに』(My Years with General Motors)を執筆している。この本は創生期から自動車を中心にした巨大コングロマリッドへと成長する過程のGMを詳細に記録しており、同時に優れた経営哲学書として今日も読み継がれている。死から1年後の1967年に自動車の殿堂入り。ちなみに日本国内でスローン主義をいち早く取り入れたのがトヨタで、トヨタ自動車販売の社長だった神谷正太郎がスローンの信奉者だったこともあり、1990年代までトヨタ流に昇華した上でスローン流の経営哲学を実践していた。
また、こうした状況を助長したのはビッグスリーに蔓延る官僚主義と利益第一主義、マーケティングとノルマ達成を信奉する数字至上主義であった(その代表がフォードの社長を務めたロバート・マクナマラであることに異論を挟む人はいないだろう)。社内では技術部門よりも財務部門が力を持つようになって社長の椅子は財務部門のトップがほぼ独占した。こうした社内環境では、アメリカ車は目に見える部分……内外装の意匠や装備の充実度、オプションの豊富さでは激しく変化する一方で、目に見えない部分……メカニズムは「消費者は新技術には興味がない」として投資が少なくなり、生産コストの増加を嫌って従来技術のブラッシュアップに終止するようになった。こうした状況にエンジニアはもちろん、現場で働く工員たちの多くは自分たちの仕事に誇りを失い、やがては製品への情熱さえも損なうようになる。
ロバート・S・マクナマラ
(1916年6月9日生~2009年7月6日没)
1916年にサンフランシスコでセールスマンの子として生まれたマクナマラは、カリフォルニア大学バークレー校で経済学を専攻(副専攻は数学と哲学)、1937年に卒業。1939年にハーバード大学のビジネススクールでMBAを取得した。その後は世界最大のコンサルティング企業・プライス・ウォーターハウスで会計士として短期間働くが、1940年にハーバート大学に戻り、ビジネススクールで教鞭を取る。第二次世界大戦が勃発すると、1943年に米陸軍航空隊に入隊。大尉として統計管理局で戦略爆撃の解析および立案の仕事に従事し、ドイツが敗北すると太平洋戦線でカーティス・ルメイ少将率いる爆撃機隊の作戦効率と効果を分析し、爆撃目標の選定とスケジュールを管理する仕事に当たった。終戦後、上官だったテックス・トーソン大佐が退役すると、統計管理局の部下たちとともに、のちに「神童たち」(With Kids)と呼ばれるグループを結成。マクナマラにも誘いがかかった。グループの一員となった彼は、創業者ヘンリー・フォード追放前後の混乱で疲弊し、フォードが財政的に逼迫していることを新聞を通じて知ると、経営立て直しのために自身らのグループを売り込み、仲間たち全員を雇わせることに成功する。そこで彼らは、赤字続きの会社が近代的な計画、組織、管理制御システムを通じて、混乱した経営体制を改革するのを助けた。マクナマラは企画および財務分析のマネージャーとしてフォードでの経歴をスタートし、その辣腕ぶりで瞬く間に昇進、最終的に社長へと上り詰める。彼がフォードで行ったのは、もっとも効率的かつ合理的な生産手段を実践するために社内にコンピューターを導入して合理化を図ったことと、綿密なマーケティングの結果をグラフを多用したスプレッドシートで“見える化”したことだった。この科学的な経営手法は1950年代には革新的なことだった。1959年秋に発表された小型車ファルコンや、1961年型リンカーン・コンチネンタルの成功は彼の手腕が遺憾なく発揮された結果であったが、マクナマラ自身はクルマにはまったく興味がなく、数字のみを信奉する人間であった。それが災いし、マーケティングに基づく完璧な新型車だったはずが、開発中にデータが古びてしまい大失敗したエドセルのような例もあった。また、数字に基づく生産の合理化は性善説に基づくものであり、ノルマを押し付けられた生産現場では数字を操作して偽りのデータを上層部に送ったことから、彼の退任直前には数字上の齟齬が生じてフォードは思うような成果を出せなくなっていた。しかし、マクナマラ自身はそうした問題に気づかず、現実を知るのはケネディ&ジョンソン政権の国防長官として、エスカレーションを続けるベトナム戦争への対応を迫られてからのことになる。
アメリカの大衆とクルマとのロマンスの終焉
商業主義と企業の論理の先行により大衆はクルマに興味を失う
第二次世界大戦に勝利し、平和の訪れとともにアメリカの大衆はクルマに夢中になった。その情熱はまさしく恋愛にも似た感情だったと言えるだろう。その熱愛ぶりは1950~60年代にかけて続いたが、やがて人々がニューモデルを追いかけ・追い続ける生活に疲れ、ふと我に返えれば、自分たちが恋焦がれていたモノの正体が冷徹な商業主義と企業の論理の産物に過ぎないことに気づいてしまう。すると、恋の魔法が溶けるように彼らの熱情はすっと冷めて行ったのだ。アメリカの大衆とクルマとのロマンスの終わりである。

その結果、何が起きたのかと言えば、カーマニアを例外としてと大衆のほとんどはクルマに飽きて興味を失ってしまったのだ。彼の国では今や自動車は人々の話題に上がることも少なくなり、大多数のアメリカ人にとっては単なる移動手段、便利な道具でしかなくなっている。彼らの心理変化に排ガス規制やオイルショックが影響したことは否定できないが、大衆がクルマに求めていたものと、企業が販売する製品との乖離は早晩あらわになっていたはずで、仮に自動車に対する逆風が起らなかったとしても、その結果にほとんど変わりはなかったことだろう。
肥大化路線と商業主義に染まる直前の一瞬の輝き
アメリカ車がもっとも幸せな時代に生まれた名車こそトライシェビー

トライシェビーが現在もなおアメリカ人の心を掴んで離さないのは、エド・コールという稀代のエンジニアが全身全霊をかけて自身の理想を体現し、完成させた傑作車というだけでなく、自動車が商業主義に完全に染りきる直前……アメリカ車がもっとも幸せだった時代に登場した名車であり、その存在が人々の胸に熱いものを刻みつけたからなのだろう。すなわち、時代が変化しようとする中で生まれた一瞬のきらめきであって、その光りは輝かしくもどこか儚さを感じさせる。
単一車種ですべてのユーザーのニーズを過不足なく賄えたトライシェビーは、基本となるポテンシャルが高く、アメリカ車としては程良いサイズにパワルフルかつ革新的なスモールブロックV8エンジンを搭載し、現代車にも通じる快適な装備を備えたことで、スポーティな走りを楽しむことも、ゆったりと快適なドライブを満喫することもできた。また、チューニングやカスタムの素材としても優秀で、HOTROD、ドラッグマシン、LOW RIDER(ローライダー)、サーファーワゴンと、オーナーが望むままあらゆる方向に改造できる懐の深さがあった。

アメリカの大衆がクルマに恋していた時代に誕生したトライシェビーは、ビッグスリーのエンジニアリングがひとつの頂点に達した時期に登場したクルマでもあり、アメリカが繁栄と平和を享受する黄金の1950年代に生まれた時代の寵児であった。その出現は歴史の必然であると同時に、さまざまな幸運が重なった奇跡でもある。
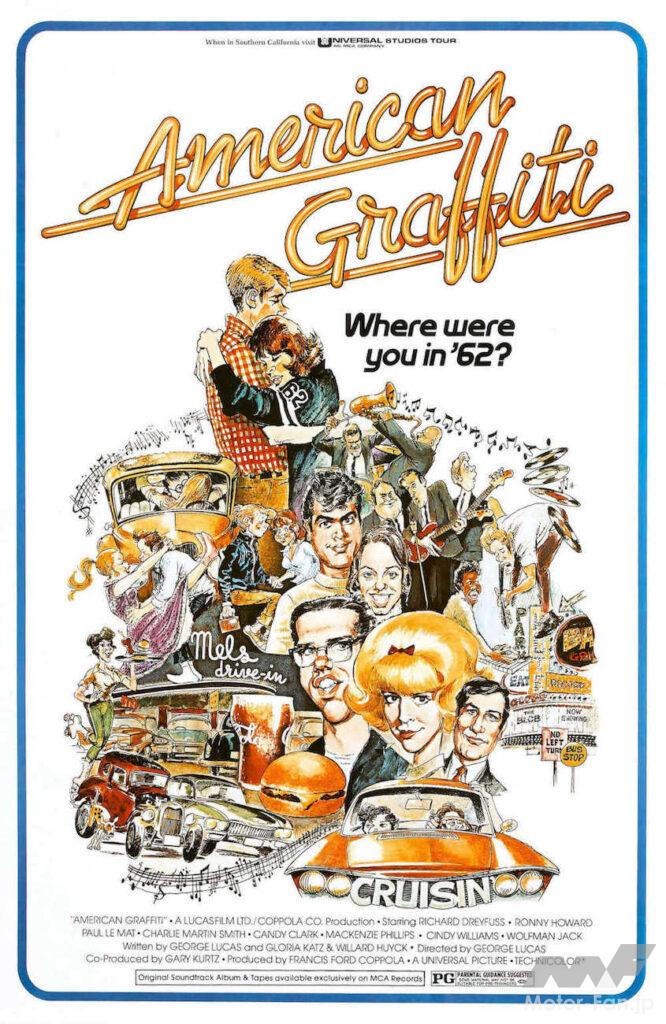
おそらく、このようなクルマは今後二度と再び現れることはないだろう。アメリカ車の永遠のアイドル・トライシェビー。このクルマはアメリカの人々と、アメリカ車を愛するファンにとっては、これからも特別な存在であり続けることは間違いない。
『トライシェビー誕生物語』シリーズを一気に読む!




















 シボレーのトライシェビーはトップグレード「ベルエア」が一番人気!? その豪華さは「ベビーキャデラック」の異名をとる
シボレーのトライシェビーはトップグレード「ベルエア」が一番人気!? その豪華さは「ベビーキャデラック」の異名をとる




 “古き良きアメリカの象徴・もっともアメリカらしいクルマ”として今も人気の「トライシェビー」はシボレー初のV8エンジン搭載モデル!
“古き良きアメリカの象徴・もっともアメリカらしいクルマ”として今も人気の「トライシェビー」はシボレー初のV8エンジン搭載モデル! 1950年代に生まれたV8 OHVエンジンの名機「シボレー・スモールブロック」は現代でも生産され続けている!?
1950年代に生まれたV8 OHVエンジンの名機「シボレー・スモールブロック」は現代でも生産され続けている!?

